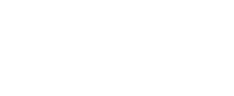会長就任挨拶
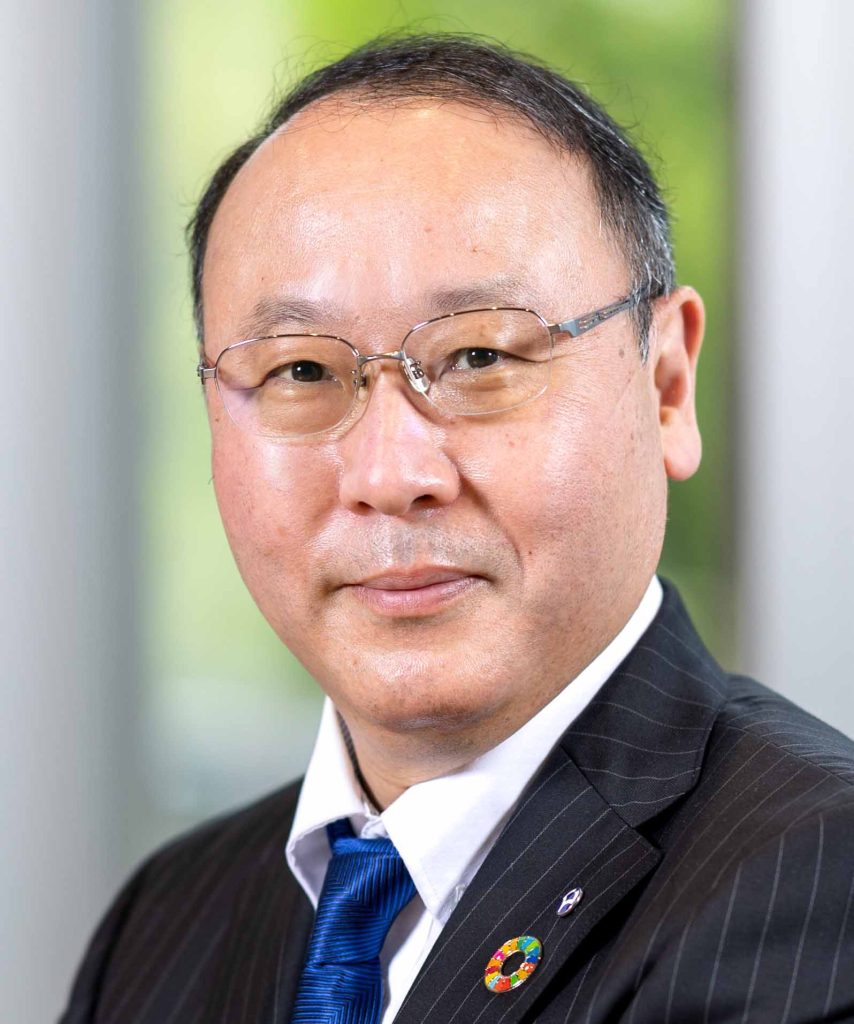
会長(代表理事)田中 学
溶接学会会長を拝命しました大阪大学の田中 学です。2年後の2026年に創立100周年を迎えるこの歴史と伝統のある溶接学会の会長にご推挙いただき、身に余る光栄に存じますとともに、その役割と責任の大きさを痛感する次第でございます。会員の皆様のご期待に応えるべく、心血を注いで任務を全うする所存です。
さて、会長就任にあたり、現在の溶接学会の会勢を会員の皆様と率直に共有したく存じます。いまの溶接学会は決して順風満帆とは言えない状況にあります。先般4月22日の総会でも報告がありましたとおり、その規模は明らかに縮小に転じています。2024年2月末時点で正員の数は2,056名であり、早晩、2千名を切ることは必至の状況であります。また、一般会計の収入では、1億円を割り、9千万円台になって参りました。大学に身を置く者としては、アカデミアの周囲を見渡し、中立研究機関に所属する溶接・接合に関わる研究者が減少しているのを目の当たりにし、実情はもっと厳しいものと感じています。
直近の歴代会長は、会員の増強はもとより、収入を増やし、支出を抑え、縮小しつつある学会に対して手を尽くしてこられました。私も理事の一人として、その対策に加わり、改善に努めて参りました。しかしながら、COVID-19パンデミックの影響を受けて学会活動に大きな制限があったことに加えて、少子高齢化に伴い18歳人口が激減し、会員の入退会バランスの崩壊に歯止めが効かない状況であります。このような学会において、会員の皆様になんとかお役に立てられることはないのか、改めて考えました。
溶接・接合技術は、ご承知のとおり、ものづくりにおいて、あらゆる製品を造る上で必要不可欠な基盤技術であります。しかしながら、社会の中で溶接・接合の価値がしっかりと評価されていないと思われます。その価値を、溶接・接合で閉じるのではなく、人工知能、ロボティクス、情報、メタバース、量子科学などといった異分野との共創(Co-creation)を通じて、新価値として見える化・見せる化させることが重要であると考えます。溶接学会は、溶接・接合技術に関わる学術の振興と発展を担う機関であり、溶接・接合の価値に力を与え、育て、新価値を創造する社会的交流の場であります。新価値の創造は、若い人達の「共感」を呼び、人が集い、技術の革新に繋がります。溶接学会は受け身ではなく、他学協会の研究者や技術者、世界中の学生や生徒を巻き込み、オープン・イノベーションの場を創って、学会自身が新しい価値を創出することが必要です。
グローバルな経済活動の下、カーボンニュートラルやグリーントランスフォーメーション(GX)の実現を背景にしつつ、学術と技術が強固な両輪となり、そこに人が加わることで溶接・接合の文化を成し、持続可能な発展を生むことができます。創立100周年に向けて、溶接学会の「新価値創造」を目標に掲げ、社会や若者たちとの溶接・接合に関わる「共感」の場を醸成できるよう、しっかり取り組んで参る所存です。
会員の皆様には、本会は勿論のこと、我が国の溶接・接合文化の発展のため、より一層のご支援ご高配を賜りますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。
2024年4月22日
さて、会長就任にあたり、現在の溶接学会の会勢を会員の皆様と率直に共有したく存じます。いまの溶接学会は決して順風満帆とは言えない状況にあります。先般4月22日の総会でも報告がありましたとおり、その規模は明らかに縮小に転じています。2024年2月末時点で正員の数は2,056名であり、早晩、2千名を切ることは必至の状況であります。また、一般会計の収入では、1億円を割り、9千万円台になって参りました。大学に身を置く者としては、アカデミアの周囲を見渡し、中立研究機関に所属する溶接・接合に関わる研究者が減少しているのを目の当たりにし、実情はもっと厳しいものと感じています。
直近の歴代会長は、会員の増強はもとより、収入を増やし、支出を抑え、縮小しつつある学会に対して手を尽くしてこられました。私も理事の一人として、その対策に加わり、改善に努めて参りました。しかしながら、COVID-19パンデミックの影響を受けて学会活動に大きな制限があったことに加えて、少子高齢化に伴い18歳人口が激減し、会員の入退会バランスの崩壊に歯止めが効かない状況であります。このような学会において、会員の皆様になんとかお役に立てられることはないのか、改めて考えました。
溶接・接合技術は、ご承知のとおり、ものづくりにおいて、あらゆる製品を造る上で必要不可欠な基盤技術であります。しかしながら、社会の中で溶接・接合の価値がしっかりと評価されていないと思われます。その価値を、溶接・接合で閉じるのではなく、人工知能、ロボティクス、情報、メタバース、量子科学などといった異分野との共創(Co-creation)を通じて、新価値として見える化・見せる化させることが重要であると考えます。溶接学会は、溶接・接合技術に関わる学術の振興と発展を担う機関であり、溶接・接合の価値に力を与え、育て、新価値を創造する社会的交流の場であります。新価値の創造は、若い人達の「共感」を呼び、人が集い、技術の革新に繋がります。溶接学会は受け身ではなく、他学協会の研究者や技術者、世界中の学生や生徒を巻き込み、オープン・イノベーションの場を創って、学会自身が新しい価値を創出することが必要です。
グローバルな経済活動の下、カーボンニュートラルやグリーントランスフォーメーション(GX)の実現を背景にしつつ、学術と技術が強固な両輪となり、そこに人が加わることで溶接・接合の文化を成し、持続可能な発展を生むことができます。創立100周年に向けて、溶接学会の「新価値創造」を目標に掲げ、社会や若者たちとの溶接・接合に関わる「共感」の場を醸成できるよう、しっかり取り組んで参る所存です。
会員の皆様には、本会は勿論のこと、我が国の溶接・接合文化の発展のため、より一層のご支援ご高配を賜りますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。
2024年4月22日